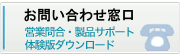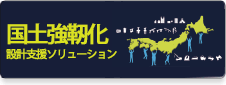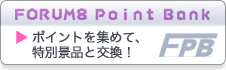|
その間、形成されてきたグループ企業を基に2006年、株式会社ACKグループを設立。2018年には現行の「株式会社オリエンタルコンサルタンツホールディングス」へと改称。同社は現在、オリエンタルコンサルタンツをはじめとする6社により構成されます。
そのうちグループの中核を成すオリエンタルコンサルタンツは現在、本社(東京)のほか10支社(北海道・東北・関東・北陸・中部・関西・中国・四国・九州・沖縄)、それらの傘下の45事務所・1環境分析センターを設置。それらに約1,160人の社員(2019年7月現在)が配置されています。また、同社は60周年を機に「社会価値創造企業」を標榜。その実現に向け、1)道路整備・保全事業、2)流域管理・保全事業、3)防災事業、4)交通運輸事業、5)地方創生事業、および6)海外事業という6つのカテゴリに分け、重点化事業として推進しています。
交通政策部の位置づけ、独自のアプローチ
重点化事業の一つ、交通運輸事業は交通技術と交通政策を柱に、高度技術や道路空間の活用による安全・円滑・快適な道路交通の実現と、地域特性を踏まえた街づくりを推進。そのうち交通政策では、日本の交通政策に基づく各種社会実験や地域交通のモビリティ確保、安全で快適な道路空間の構築や街づくりなどに取り組んでいます。
今回ご紹介する交通政策部は、関東支社の管理下にあり、8割方は支社管内の顧客向け業務が占める(後藤氏)一方、本社の交通運輸事業部で決められた方針に基づき全国横断的な検討にも対応。40名弱の社員がITS(高度道路交通システム)や自動運転、交通計画、運用後の道路の課題などの検討に携わっています。
同部が近年ウェートを置く課題として、後藤氏は戦略的なマニュアル作りのアプローチに触れます。例えばラウンドアバウトのような、海外で成功している道路施設を国内に導入するようなケースで、「マニュアルが出来てから(既存のマニュアルを)使う」のではなく、「マニュアルを作るところから関わる」。
つまり、そのような施設を設計する際に、マニュアルを単に使う側としてではなく、日本独自のデータも反映しながらマニュアルを作る側の視点でしっかり検討しようとの考え方が定着してきています。
また、交通インフラを扱う上で、交通量や速度、個々の車両の移動状況などに関する基礎的な情報は非常に重要。そうした認識から、それらの情報を取得するためのセンサーや機械の自社開発にも一貫して力を入れているといいます。
案内誘導や道路情報板など多様な施策検討でUC-win/Road DS活用
同部において渋滞対策など交通の円滑化や交通安全に関わる分野の検討および提案を主に担当する後藤氏は、これまでに自身はもちろん、部内の各種プロジェクトを通じ多様なUC-win/Road DSの活用に接してきた、と振り返ります。
後藤氏が最初にUC-win/Road DSを適用する業務に携わったのは、冒頭で挙げた首都高速道路大橋JCTのプロジェクトです。これは、都心部の限られた用地条件の中で中央環状線の地下トンネル(山手トンネル)と高速3号渋谷線を接続。様々な難題に対し、高低差約70mを一周約400mのループ形状2周4層で連結し、地上のループ部を構造物で覆う覆蓋構造として計画されました。過去に例のない特殊な構造で、ドライバーの空間認知能力の低下やストレスの増大などが懸念されたこともあり、同社はそのソリューションとして色を用いた案内誘導施策を提案(2008年)しています。
「色を使った案内誘導が有効であろうことは、分かっていました」。後藤氏はその数年前、羽田空港の第1旅客ターミナルと第2旅客ターミナルの案内誘導に関する検討を担当。その際、色を利 用して目的地へ誘導する施策を提案。当時はCGで作成した動画を利用者らに見てもらう実験を行い、その有効性を実証。施策が採用された経緯がありました。
そこでの経験を背景に大橋JCTのプロジェクトでは、例えば3号渋谷線の分岐で郊外の東名方面を「青色」、都心方面を「赤色」で案内し、ドライバーが路面の色を見て走行すると目的地方面へ確実に分岐行動できるよう意図。併せて、事故対策用のラバーポールやカーブ警戒ゼブラ板などの色も当該道路空間全体でデザイン統一することを提案。施策の有効性を検証するため、UC-win/Road DSを導入。ただ、施策の見え方(色)の再現には制約があったことから、採用する色の決定や施策の見え方の検証のため、建設現場の一部で実際の素材を利用するなどして実験を行っています。
同プロジェクトを通じ、完成後の環境を事前に再現し、容易にいろいろなパターンを試行できるUC-win/Road DSのメリットを認識。以後も複数事業で同DSの利用が重ねられており、近年では例えば、ヘッドマウントディスプレイ(HMD)を用いたトンネル火災時の避難体験用DSの開発、高速道路の情報板から走行中のドライバーが読み取れる情報量の検討などにも活用されています。
UC-win/Road DS活用の広がる可能性
「(VR)DSって、利用者が体験するという意味で、(多目的に使える)結構有効なツールなのです」
例えば、一定区間の道路をVRで作成してしまえば、コンサルティングの検討に使えるのをはじめ、後の協議段階で完成後の環境を再現して見せて合意形成を得やすくすることも可能。また、イベントなどの広報活動に用いればエンターテインメント的な要素を持たせつつ教育用としても使える、と後藤氏はそのもたらす広範な用途を挙げます。
つまり、世の中にまだ実現していないものを作るケースはもちろん、基準作りのようにある程度バリエーションを持たせた事例について検討しなければならないケース、あるいは交通のモードを切り替えて検討するケースなどへの対応も視野に入れます。
さらに、街自体をVRで作ってしまえば、VR環境の中でコミュニケーションを図りつつ様々な活動に繋げていけるのでは、と言及。そこでは、精度が上がれば上がるほど、活用の可能性は広がるはず、との見方を示します。
ユーザー側のスタンスとVR技術の発展
VR環境はリアルのものでない以上、おそらく「100点というのはない」と後藤氏は述べます。そのため利用の仕方によりベストを尽くす。併せて、例えば現行のDSで何が足りないかをニーズとしてフォーラムエイト側にしっかりと伝え、将来的に少しでも100点に近づいていけるよう目指せば良い、とのスタンスを説きます。そこには、そうしたアプローチを反映し、これまで着実に画像のリアリティが向上し、モニターの数や位置の改善などが図られることで実際の運転環境により近い再現が可能になってきた、との自負があります。
つまり、現行のDSで「出来ないから」と諦めるのではなく、「どういうことをしてもらいたい」というニーズを積み上げていくことで、VR技術やDS自体が益々進化し、そのもたらす再現性もさらに現実に近づいていく。そうした技術が集積する先には、前述の「バーチャルな街」のようなものの実現性も高まるのでは、といいます。
「(VRやAIの高度化がカギとなる世界は)技術的にはどんどん発展できる分野だと思うのです。(その意味からもユーザー側としては)要望を言い続けていけば良いのではないかなと」
 |
| 関東支社交通政策部安全・円滑チームの皆さん |
|